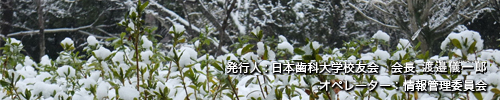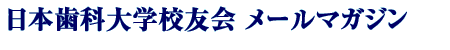 |
第453号 2020年4月27日 |

| 令和2年 | ||
| 5月25日(月) | 遠隔授業開始 東京校 |
コロナウイルス感染拡大のために、大学の5月教務日程が上記以外は発表されていません。
また、校友会本部の事業、出張等も未定となっています。
1.役員会からの掲示板を更新しました。(4/21・22)
2.メールマガジン452号を掲載しました。(4/15)
*趣味の世界で異能を発揮している校友の情報をお寄せ下さい 自薦・他薦可
ホームページ「Hobbyな人々」に掲載します

| 1.第133回通常総会について |
日歯大校第100号 令和2年4月21日 日頃より本会にご尽力を賜りまして、まことにありがとうございます。 |
| 2.互助事業休止のお知らせ 4月21日 |
互助事業(歯科医師派遣)休止のお知らせ 日本歯科大学校友会 会長 近藤勝洪 新型コロナウイルス感染拡大にともなう緊急事態宣言発令により歯科医師派遣を休止しております。 以上 |
| 3.始業について(在学生通知) 4月21日 |
日本歯科大学 生命歯学部長 沼部幸博
以上 |
4.入学式の取り止めおよび始業について(新入生通知) |
周知の通り、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、入学式を5月7日(木)に延期しましたが、東京において未だ感染拡大は続いており、終息の兆しは見えておりません。 生命歯学部 周知の通り、新型コロナウイルスの感染拡大は続いており、収束の兆しは見えておりません。 新潟生命歯学部 |
| 5.辞令 |
4月1日に発令された辞令の一部を掲載する なお、生命歯学部の沼部幸博学部長と五十嵐 勝教務部長に変更はない |
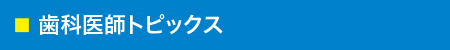
| 1.シャープ、マスク販売でアクセス集中 接続困難に 日本経済新聞 電子版 4月21日 |
シャープが21日10時に開設したマスク販売の専用サイトにアクセスが集中し、同11時現在でも接続しにくい状況が続いている。マスクはドラッグストアなどで品薄状態が続いており、購入者が殺到したとみられる。会社側は「状況を確認している最中だ」としている。 |
| 2.新型コロナ・同時進行ドキュメント 台東の診療所 患者と距離感、ため息 毎日新聞 4月21日 |
4月20日午後3時半、東京都台東区の蔵前協立診療所にはせきなどの症状を訴える70代の女性患者が訪れた。既に平熱に戻っていたが、2日前に38度の熱が出たという。原田文植医師(48)は「新型コロナウイルスかもしれない」と考え、念のためレントゲン撮影もしたが、コロナでないと診断した。 |
| 3.保健所介さぬPCR検査、広がるか 医師会連帯で迅速化 朝日新聞 デジタル 4月21日 |
新型コロナウイルスに感染しているか調べるPCR検査が追いついていない現状を改善しようと、検査数を増やす取り組みが始まろうとしている。保健所を介さず、迅速に検査を受けられる態勢が今後、全国に広がっていく可能性がある。感染の拡大を防ぐため、地域をあげての対応が急がれている。 |
| 4.ロシュの新型コロナ抗体検査薬、日本で5月めど申請へ 日本経済新聞 電子版 4月20日 |
スイスの製薬大手ロシュの診断薬事業部門の日本法人であるロシュ・ダイアグノステイックス(東京・港)は20日、ロシュが開発中の新型コロナウイルスの抗体検査薬を日本でも5月中をめどに承認申請する方針を明らかにした。抗体の有無を調べることで、新型コロナウイルスに対する免疫を獲得している人を見つけることができる。 |
| 5.後期高齢者、保険料月439円増 毎日新聞 4月18日 |
厚生労働省は17日、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度について、4月からの2年間の保険料見込み額を公表した。全国平均で月6397円となり、2018~19年度に比べ439円(7.4%)増える。年額では7万6764円で、5272円増。全都道府県でアップする。保険料の増加は、比較的所得の低い人などを対象とした特例的な軽減措置の縮小が大きな要因。 |

| 校友会会費納入の確認について |
※新卒者は入会時に4年分の会費を納めていただいております。5年目(来年は106回卒)からの会費納入をお忘れないようにお願いいたします。その後2年間未納の方は自然退会となりますのでご注意ください。 最近、送付物等が校友会から届かない会員の方は、事務局までお問い合わせください。 |
| 校友会会員専用ページ |
| 会員のみが閲覧できる専用のページがあります。校友会本部HP上で、「会報バックナンバー」の表示をクリックしたときに「ユーザー名」欄、「パスワード」欄のある画像が出ましたら校友会・歯学会会報のクリップボードに掲載されている記号数字をそれぞれ半角で入力をお願い致します。ユーザー名およびパスワードは大切に保存をお願い致します。 |
| メールアドレス登録・再登録のお願い |
| 校友会本部では、インターネットが会員への情報伝達を効率化、迅速化する上で有力な手段であると考えています。ぜひとも大多数の会員が本会から発せられるインターネットでの情報を受信できるよう、普及にご協力ください。お知り合いの会員で、まだ登録されていない、あるいは登録したけれどもメールマガジンが届かないという方がいらっしゃいましたら、 校友会本部HP(http://www.koyu-ndu.gr.jp/)でのメールマガジン登録あるいは再登録をお勧めください。 |