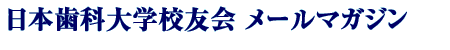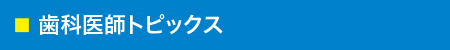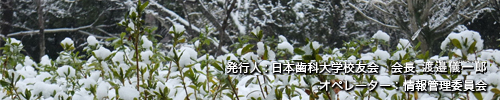|
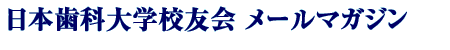 |
第449号 2020年2月25日 |
|

| 令和2年 |
|
|
| 2月26日(水) |
|
・4年CBT追再試験 新潟校 |
| 27日(木) |
|
・4年OSCE追再試験 新潟校 |
| 3月4日(水) |
|
・109回卒業式 10時 東京校 |
| 3月6日(金) |
|
・109回卒業式 11時 新潟校 |
| 3月9日(月) |
|
・1〜5年進級審査 東京校 |
| 11日(水) |
|
・4年臨床実習オリエンテーション(〜13日)東京校 |
| 12日(木) |
|
・1〜5年進級審査 新潟校 |
| 16日(月) |
|
・4年臨床実習開始 東京校
第113回歯科医師国家試験合格発表 |
| 29日(土) |
|
栃木県校友会「東京・新潟をつなぐ会」13時 宇都宮市 チサンホテル宇都宮 |
| 30日(月) |
|
・5年病院実習引き継ぎ(〜31日) 新潟校 |
|
| |

http://www.koyu-ndu.gr.jp
1.求人案内情報を更新しました。(2/12)
2.役員会からの掲示板を更新しました。(2/10)
3.メールマガジン448号を掲載しました。(2/10)
*趣味の世界で異能を発揮している校友の情報をお寄せ下さい 自薦・他薦可
ホームページ「Hobbyな人々」に掲載します
|
| |

| 1.D Muse 2020 設立10周年記念 申込開始 |
今年、設立10周年を迎えた「D Muse」は4月26日(日)に開催されることは前々号で紹介しましたが、すでに申込が開始されていますのでお知らせします。校友会ホームページには申込サイトが開設されています。FAXをご利用の先生は2月に発行されている校友会・歯学会会報の申込方法が記載されていますのでご覧ください。申込みはすべて事前に必要で、当日参加は受付けておりませんのでよろしくお願いいたします。
|
2.学術フォーラム2020 申込期限を延長 |
3月15日(日)に開催される学術フォーラム2020の事前申込が2月27日(木)で締め切られますが、今まで臨床研修医の皆さんが受講できなかったテーブルクリニック3「ビギナーのための歯科用CBCT講座 正しい三次元画像の操作画像観察手順の習得」が受講できることになりました。申込みは校友会ホームページの申込サイトからお願いいたします。
中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルス(COVID-19)の感染が国内でも広がり始めて、コンサートやスポーツイベントの中止がみられるようになってきました。校友会本部では感染の広がり状況や政府の対応の変化に注視し、学術フォーラムの開催を中止するかを今月中に発表いたします。開催しても、発熱・せき・全身の倦怠感の症状のある先生方は来場することができません。参加者全員がマスクを着用し、こまめな手指の消毒が必要で、換気のために窓を開けるために厚着での来場が必要になります。
|
|
|
|
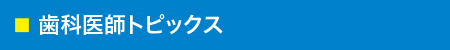
1.高齢者医療費、負担どうなる「2割なら貯金取り崩し必要」「少子化・・現役で支えきれぬ」
毎日新聞 2月19日 |
高齢化に伴う医療費の急増に対応するため、厚生労働省は1月から公的医療保険制度の改正に向けた議論を始めた。既に政府は、75歳以上で一定以上の所得がある人の窓口負担を1割から2割に引き上げる方針を決めているが、具体的にどの所得層で線引きするかが最大の焦点だ。それ以外にも、今の医療制度を維持するための見直しが盛り込まれている。
2月中旬。内科や耳鼻科など複数の診療所が入居している東京都府中市のビル。つえやシルバーカーを頼りに歩く、多くのお年寄りが訪れていた。地元に住む男性(83)は膝の関節炎で整形外科を受診し、窓口で1割の110円を支払った。男性は、月35万円の年金と年80万円の不動産収入がある。それでも「脳梗塞や認知症を患う妻の入院費も高い。2割になればどんどん貯金を崩さないといけない」と不安が募る。
一方、同じビルにある小児科クリニックに子連れで訪れた女性(37)は「子どもが少なくなり、高齢者の医療費を支えられなくなっている。もっと負担をお願いしたい」と話す。75歳以上が対象の後期高齢者医療制度の自己負担は原則1割で、若い世代の3割より低い。政府の「全世代型社会保障検討会議」は昨年12月の中間報告で、75歳以上でも一定以上の所得で2割に引き上げると決めた。
75歳以上の医療費は8割強(約15兆円)を若い世代の保険料と国・自治体の公費で賄っている。75歳以上になると持病を抱え、医療費がかさみがち。一方、若い世代は保険料を払っても高齢者ほど医療機関を受診する機会は少ない。政府が見据えるのは、人口の多い団塊の世代(1947〜49年生まれ)が75歳になり始める2022年だ。政府推計では、医療費は18年度の45兆円から25年度には54兆円に膨らむ。若い世代の人口が急に増える見通しはない。そのまま放置すれば、現役世代に負担が重くのしかかる構図だ。
ただ、これまで1割だった人が2割となれば、負担感は倍増する。境目となる所得層の線引きを託されたのが、厚労相の諮問機関「社会保障審議会医療保険部会」だ。75歳以上の医療費自己負担は、所得水準によって▽「現役並み」(年収383万円以上=3割)▽「一般」(年収155万〜383万円=1割)▽「低所得者(年収155万円以下=1割だが、自己負担の上限額を一般より低く設定)に分かれている。現役並みは7%、一般は52%、低所得者は41%程度だ。自民党は2割となる対象範囲を明確に示していないが、公明党は低所得者への配慮で「原則1割負担」の維持を求める。
1970〜80年代、国は高齢者の医療費自己負担を無料としていた。しかし、医療費がかさみ、再び一部負担を求める制度に戻った。老人保健制度だった2001年、70歳以上を対象に初めて1割の定率負担を導入。それ以降、原則1割(08年の後期高齢者医療制度導入に伴い70〜74歳は2割)の時代が長く続いてきた。今後は後期高齢者の収入や支出といった生活実態から可能な負担を分析し、2割の範囲を決定する。ただ、75歳以上は年金を生活の糧とする人が大半。独居も増えつつあり、年金から介護費用を負担する人も少なくない。厚労省幹部は「低所得者を2割に引き上げるのは生活への影響が大きく、難しい」と話す。
足りぬ財源、見えぬ方策
国の医療保険財政の悪化を避けるべく、国が打ち出した対策は他にもある。その一つが診療所などの紹介状なしに大病院を受診した際、初診で5000円以上の追加負担を求める対象病院をさらに拡大する案だ。大病院へ集中しがちな外来患者を診療所や中小病院にも振り分けて、大病院をより高度な医療や救急に専念させる。 もともと政府は、大学病院や地域の拠点病院のうちベッド数が400床以上(420病院)で追加負担を求めていたのを、4月から200床以上(約670病院)へと拡大する方針だった。政府はさらに200床以上の一般病院にも広げた上で、負担額も5000円からさらに増やす。増額分は、保険給付を減らすなどの方法で医療保険財政への負担を軽くする。
200床以上の一般病院は2000前後に及ぶが、「かかりつけ医」など地方で地域住民に密着した診療を担っている病院もある。病院団体から「かかりつけの病院に5000円を払わないとかかれなくなれば、医療崩壊を招きかねない」(相沢孝夫・日本病院会会長)との批判が出ている。
厚労省はこうした声を踏まえ、定額負担の対象を専門的な医療を担う病院などに絞り込む方針だ。ただし、定額負担の対象になれば外来患者が減る可能性もある。病院の収益は減り、患者の医療へのアクセスも悪化しかねず、調整が難航することが予想される。厚労省は夏まで議論し、今秋の臨時国会に関連法案を提出。22年度からの実施を目指す。22年度以降は毎年8000億円ほど社会保障費が増加すると見込まれるが、厚労省幹部は「(改革案で)恐らく何千億円もの医療費削減効果は出ない。財務省から追加の対応を求められるだろう」とみる。
|
2.WHO「マスクや手袋の不足心配」需要100倍、価格20倍
日本経済新聞 電子版 2月8日 |
世界保健機関(WHO)は7日、マスクや手袋などの個人防護用品の不足が深刻になっていると警鐘を鳴らした。新型コロナウイルスの感染を恐れる顧客の買いだめなどが一因とみられる。WHOは特に最前線で働く医療関係者に十分にいき渡っていないとし、各国や企業と協力して対策を急ぐ方針だ。
WHOは個人防護用品の需要は通常時に比べ最大100倍、価格は同20倍になっていると分析した。インターネットではマスクなどが高額出品されているケースも目立つ。テドロス事務局長は会見で「個人防護用品の市場は深刻な混乱に陥っている」と指摘した。患者をケアするために使うのが最も重要だが、「それ以外の不適切な使用によって状況が悪化している」という。在庫は枯渇しつつあるといい、感染が少ない地域での備蓄は推奨しないとも強調した。
|
3.勤務時間減らす病院に加算を 診療報酬見直しを答申
朝日新聞 デジタル 2月8日 |
4月からの保険診療の範囲と料金が決まった。診療報酬の見直し方を7日、厚生労働省の中央社会保険医療協議会が答申した。医師の働き方改革のほか、病院の役割分担や再編・統合も後押しする。団塊世代が75歳以上になる2025年が迫るなか、医療の構造転換を進める狙いがある。
当直明けたら また当直
30代の男性医師は昨年まで3年間、関東地方の救命救急センターの救急医だった。24時間の受け入れ態勢を支え、勤務は月250〜300時間。経験を積むため、当直明けのまま、人手を求めている別の病院の当直に入る「2泊3日」の勤務になることもあった。仮眠を挟みつつも、最長39時間の連続勤務。「私はまだ、代休が取りやすかったので恵まれていた」
24年度から、医師にも残業時間の上限規制が適用される。救急をはじめ勤務医のハードな働き方を見直し、医療現場の安全向上や人材確保につなげるため、2年に1度の今回の改定では、勤務医の時間外労働を減らす計画を作った病院に報酬が入る新たな加算を作る。救急搬送が年2千件以上の病院が対象で、入院1回につき患者に1560円(自己負担3割の場合)を求める。病院には1人につき5200円が入る計算で、増えた報酬を財源に、医師の増員などを進めてもらう狙いがある。
事務スタッフ増やせば変わる?
仕事の分担や効率化も進めるため、医師の事務作業を支えるスタッフを置いた場合の加算を引き上げる。対象病院などの入院患者には、入院1回につき150円(同)の負担増になる。すでに現場では、こうした事務スタッフを置く取り組みが進んでいる。「調子はどうですか?」石川県野々市(ののいち)市の金沢脳神経外科病院(220床)の診察室で、佐藤秀次院長が患者に語りかけた。その隣で事務補助のスタッフ「クラーク」が、医師と患者のやり取りを電子カルテに入力していく。診察の最後、医師が処方薬を入力している間に、クラークは患者と次回の診察日程を決めた。
専門病院のため専門医が多く必要だが、確保が難しく、診療報酬に事務スタッフ配置への加算ができた翌年の09年に、医師の負担を減らそうとクラークを導入した。現在、常勤医18人に対してクラークは14人。患者から求められる診断書もクラークが作り、医師は最終チェックだけですむという。脳神経外科の飯田隆昭部長は、クラークは「すでになくてはならない存在」と話す。医師が書類作成で残業や休日出勤をする必要がなくなり、時間外の診察や病棟の回診でもクラークを活用できれば、もっと医師の負担を減らせると期待する。ただ、診療報酬だけでは今の配置人数はまかなえず、すでにクラークの人材不足や質の確保も課題となっている。
追加料金取れば…ジレンマ
医療の効率化に向け、政府は診療報酬の仕組みを使って病院改革も進める。患者が大病院に集中するのを避けるため、紹介状なしの患者は追加料金が原則必要になる病院を、今の400床以上から200床以上に広げる。今は初診で5千円以上で、病院ごとに異なる。政府の全世代型社会保障検討会議では金額引き上げ方針も示されており、夏までに具体額を詰める。
ただ、懸念もある。病院団体の一つ「日本病院会」が会員病院に調査したとこ「(追加料金を取れば)患者が減って病院が存続できない」「抜け道として、病院の近くに系列の『門前クリニック』を作って追加料金を逃れるだけでは」などの指摘もあった。相沢孝夫会長は「地域医療に深刻な影響を及ぼす可能性がある。病床数で区切るのも疑問で、むしろ病院の機能をどう変えるか議論する必要がある」と話す。
「かかりつけ医、浸透してない」
その病院の機能を、かかりつけ医との役割分担を進めて転換していけるかも課題だ。人口減少が進む中、25年に必要な入院ベッド数は、今より5万床ほど少ない119万床と推計されている。厚労省は、地域内で役割の似ている病院などの再編・統合を促す「地域医療構想」を進めている。少子高齢化で、急患の病床よりも慢性疾患の病床のニーズが高まるため、病床の数と種類を共に変える必要がある。そこで今回の改定では、総合病院としての加算を得ている病院が、地域ニーズが低くなった小児科や産科などの診療科を他の医療機関と統合して入院の受け入れをやめても、引き続き総合病院としての加算を認めることなども盛り込んだ。
ただ、日本総研の西沢和彦主席研究員は「大病院を受診するのは、かかりつけ医が浸透していないことの裏返し。政府の構想は、地域に頼りになる開業医がいることが前提だが、国民はそう実感できておらず、重要なピースが欠けている」と指摘する。「診療報酬での誘導は限界があり、地域の医師と国民を結びつける取り組みが必要だ。」
|
|
| |

| 校友会会費納入の確認について |
※新卒者は入会時に4年分の会費を納めていただいております。5年目(来年は105回卒)からの会費納入をお忘れないようにお願いいたします。その後2年間未納の方は自然退会となりますのでご注意ください。
最近、送付物等が校友会から届かない会員の方は、事務局までお問い合わせください。 |
| |
| 校友会会員専用ページ |
| 会員のみが閲覧できる専用のページがあります。校友会本部HP上で、「会報バックナンバー」の表示をクリックしたときに「ユーザー名」欄、「パスワード」欄のある画像が出ましたら校友会・歯学会会報のクリップボードに掲載されている記号数字をそれぞれ半角で入力をお願い致します。ユーザー名およびパスワードは大切に保存をお願い致します。 |
| |
| メールアドレス登録・再登録のお願い |
| 校友会本部では、インターネットが会員への情報伝達を効率化、迅速化する上で有力な手段であると考えています。ぜひとも大多数の会員が本会から発せられるインターネットでの情報を受信できるよう、普及にご協力ください。お知り合いの会員で、まだ登録されていない、あるいは登録したけれどもメールマガジンが届かないという方がいらっしゃいましたら、 校友会本部HP(http://www.koyu-ndu.gr.jp/)でのメールマガジン登録あるいは再登録をお勧めください。 |
|
|
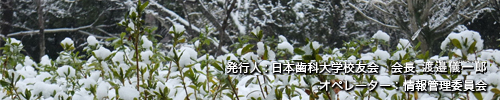 |

バックナンバーはこちらから |