
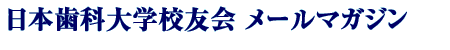 |
第428号 2019年4月1日 |

| 平成31年 | ||
| 4月1日(月) | ・5年臨床実習開始 東京校 | |
| 2日(火) | ・5・6年オリエンテーション 5年登院式 新潟校 | |
| 3日(水) | ・新潟生命歯学部 入学式 5年病院実習開始 6年学力模試 新潟校 ・2〜6年前期授業開始 東京校 |
|
| 4年(木) | ・新入生オリエンテーション 2〜4,6年進級オリエンテーション 新潟校 ・新入生オリエンテーション(〜6日・合宿)2〜4,6年前期授業開始 新潟校 |
|
| 5日(金) | ・生命歯学部 入学式 東京校 | |
| 6日(土) | 大分県校友会定時総会 15時 大分市 ホテル日航大分オアシスタワー | |
| 8日(月) | ・1年オリエンテーション 東京校 ・1年前期授業開始 新潟校 |
|
| 9日(火) | ・1年ワークショップ 東京校 | |
| 10日(水) | ・1年袖ヶ浦セミナー 東京校 | |
| 11日(木) | ・1年前期授業開始 東京校 | |
| 12日(金) | ・新入生歓迎会 学生会主催 新潟校 | |
| 13日(土) | ・新入生歓迎会 14時 東京校 富士見ホール ・1年GTEC GPS 東京校 |
|
| 19日(金) | ・解剖体慰霊祭 | |
| 20日(土) | 体育会設立50周年記念祝賀会 18時 ホテルメトロポリタンエドモント | |
| 21日(日) | D Muse 2019 10時半 九段ホール 群馬県校友会総会懇親会 16時半 高崎市 ホテルグランビュー高崎 |
|
| 26日(金) | ・4年富士見・浜浦フェスタ(〜27日)福島県 | |
| 27日(土) | ・学生合同合宿・クラブ活動週間(〜5/1) 校友会スポーツ・文化・学術大賞表彰式 14時 猪苗代町 学びいな |
|
| 5月 9日(木) | ・3年校友会特別講義 東京校 18時半 九段ホール | |
| 11日(土) | ・5・6年全国統一模擬試験 東京校 兵庫県校友会定時総会 17時 神戸市 神仙閣 |
|
| 16日(木) | ・3年校友会特別講義 新潟校 15時 アイヴイホール | |
| 18日(土) | 静岡県校友会総会学術講演会 17:15 静岡市 ホテルアソシア静岡 | |
| 23日(木) | ・1〜6年学生健康診断 東京校 | |
| 25日(土) | ・6年本試験①(〜26日) 新潟校 |
1.中原泉 一枚の写真を更新しました。(3/27)
2.バックナンバー校友会歯学会会報・KOYUTimesを更新しました。(3/20)
3.役員会からの掲示板を更新しました。(3/19・27)
4.メールマガジン427号を掲載しました。(3/18)
*趣味の世界で異能を発揮している校友の情報をお寄せ下さい 自薦・他薦可
ホームページ「Hobbyな人々」に掲載します

| 1.光安一夫 前校友会会長 永眠される | ||||||||||||||||||||||||
平成31年3月25日に光安一夫名誉会員・前会長(平成13年11月から23年5月まで会長就任)がご逝去された。通夜は3月31日(日)に、葬儀・告別式は4月1日(月)に東京都中野区の宝仙寺大師堂で営まれた。喪主は長男の光安廣記(79回)先生で、通夜には校友会会員等の200余名が会葬した。告別式で近藤勝洪校友会会長は弔辞で次のように述べた。
※画像が見られない方はこちら
|
||||||||||||||||||||||||
| 2.D Muse 2019 参加申込枠拡大・延長のお知らせ | ||||||||||||||||||||||||
たくさんの方から参加希望のお問い合わせをいただいていることから、今回は「本学卒業の女性歯科医師」に限らず、男性歯科医師、歯科衛生士の方も参加可能とさせていただきました。認知症患者さんのケアに携わる方を始め、一人でも多くの方に聴講していただきたいと思います。皆様、奮ってご参加ください。
|
||||||||||||||||||||||||
| 3.冬季歯学体の結果 | ||||||||||||||||||||||||
今年の冬期歯学体は、平成30年12月28・29日東福岡高校グラウンドで開催されたラグビーフットボール部門で生命歯学部ラグビー部が準優勝し、平成31年3月17〜21日に群馬県妻恋村鹿沢スキー場で開催されたスキー部門で新潟生命歯学部スキー部が男子団体戦で優勝し、総合団体戦は準優勝であった。
※画像が見られない方はこちら |
||||||||||||||||||||||||
| 4.第112回歯科医師国家試験の合格発表について | ||||||||||||||||||||||||
平成31年2月2日(土)、3日(日)に全国7カ所で実施した第112回歯科医師国家試験の合格者は3月18日に発表されました。
歯科医師国家試験の合格者数は第107回(平成26年)以降6年連続で2千人前後であり、合格率は63~65%と低率であるが、今回、新潟生命歯学部の新卒者の合格率93.9%は学校別で全国で4位でした。 学校別合格者状況は校友会ホームページに記載されています
|
||||||||||||||||||||||||
| 5.日歯代議員会 開催される | ||||||||||||||||||||||||
日本歯科医師会は3月14・15日の両日、第189回臨時代議員会を東京都千代田区の歯科医師会館で開いた。平成31年度の事業計画や入会金および会費の額、収支予算の件など全4議案を賛成多数で可決した。議案可決後、7題の地区代表質問と29題の個人質問について執行部が答弁した。 |
||||||||||||||||||||||||
| 6.「日本歯科大学体育会設立50周年記念祝賀会」開催のご案内 | ||||||||||||||||||||||||
昭和44年に「日本歯科大学体育会」に名称を改めて、早50年の歳月が流れようとしています。平成26年に「日本歯科大学体育会設立45周年記念祝賀会」を元役員主体に開催いたしましたが、今回の50周年は大きな節目となります。元役員のみならず、各クラブOBにお声がけをして、クラブの枠を越えて広く再会する機会にしたいと思います。 日本歯科大学体育会設立50周年記念祝賀会
|
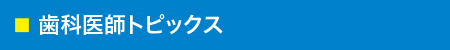
| 1.くらしナビ・ライフスタイル 乳歯の思い出いつまでも 3月25日 毎日新聞 |
子どもの乳歯が抜けたら、どうする? 上の歯が抜けたら床下に、下の歯が抜けたら屋根の上に投げる、という風習はよく知られているが、乳歯を投げずに自宅で保管したり、再生医療に活用したりする人たちもいる。今どきの乳歯事情を探った。 |
| 2.診療明細、国保連合会が審査を省略 医療費過払いの恐れ 3月20日 朝日新聞 デジタル |
国民健康保険の加入者の医療費を支払う国民健康保険団体連合会(国保連合会)が、病院などから提出された診療報酬明細書(レセプト)の内容に誤りがないかについて、必要なチェックを省略していたケースがあることが、会計検査院の調べでわかった。レセプトの誤りが見過ごされ、医療費の支払いが過大になっていた可能性があるという。 |
| 3.19年医師国家試験に9.029人が合格、合格率は89.0% 3月18日 厚生労働省 |
厚生労働省は3月18日、2019年2月に実施した第113回医師国家試験の結果を発表した。受験者数1万146人(前年比136人増)に対し、合格者数は9,029人(5人増)。合格率は前年から1.1ポイント減の89.0%となった。合格者の男女別内訳は、男性6,029人(構成比66.8%)、女性3,000人(33.2%)。男女別合格率は、男性88.1%、女性90.8%だった。合格者のうち新卒者は8,478人、合格率は92.4%だった。既卒者の受験回数別合格率は、2回目73.1%、3回目51.5%、4回目34.3%などとなっている。 |
| 4.会員有功章授与式 開催される 3月15日 日本歯科医師会 |
日本歯科医師会は平成30年度会員有功章授与式を3月15日に歯科医師会館で開いた。4人の受賞者のうち、「困難なる環境の中で、30年以上診療に従事し、地域社会の歯科保健衛生の向上に特に著しい功労があったと認められる者」の該当者に沖縄県の上原淳(56回)氏が選ばれた。 |
| 5.歯の再生医療の安全性と効果は?順天堂大チームが臨床研究へ 3月15日 毎日新聞 |
濃縮した血小板(PRP)を使う歯科の再生医療について、順天堂大の飛田守邦准教授(口腔外科学)のチームは15日、安全性を検証し、効果もみる臨床研究を厚生労働省に届け出た。同様の再生医療は、再生医療安全性確保法に基づき全国で行われているが、臨床研究が実施されていないケースがあり、専門家から「安全性や効果が担保されていない」などの指摘があった。 |
| 6.診療データ共有形骸化 公費530億円投入でも登録1% 3月14日 日本経済新聞 電子版 |
IT(情報技術)を活用した医療の効率化がかけ声倒れになっている。診療データを病院間で共有する全国約210の地域ネットワークの登録患者数は、国内人口のわずか1%であることがわかった。国と自治体は医療責の抑制や患者の利便性向上を狙い、計530億円を超す公費を投じたが、重複医療を解消する効果が出ていない。医療IT政策の仕切り直しが必要だ。 |

| 校友会会費納入の確認について |
※新卒者は入会時に4年分の会費を納めていただいております。 4年後(今年は104回卒)からの会費納入をお忘れないようにお願いいたします。 その後2年間未納の方は自然退会となりますのでご注意ください。 最近、送付物等が校友会から届かない会員の方は、事務局までお問い合わせください。 |
| 校友会会員専用ページ |
| 会員のみが閲覧できる専用のページがあります。校友会本部HP上で、「会報バックナンバー」の表示をクリックしたときに「ユーザー名」欄、「パスワード」欄のある画像が出ましたら校友会・歯学会会報のクリップボードに掲載されている記号数字をそれぞれ半角で入力をお願い致します。 このページからコピー&ペーストされても結構です。ユーザー名およびパスワードは大切に保存をお願い致します。 |
| メールアドレス登録・再登録のお願い |
| 校友会本部では、インターネットが会員への情報伝達を効率化、迅速化する上で有力な手段であると考えています。ぜひとも大多数の会員が本会から発せられるインターネットでの情報を受信できるよう、普及にご協力ください。お知り合いの会員で、まだ登録されていない、あるいは登録したけれどもメールマガジンが届かないという方がいらっしゃいましたら、 校友会本部HP(http://www.koyu-ndu.gr.jp/)でのメールマガジン登録あるいは再登録をお勧めください。 |




