
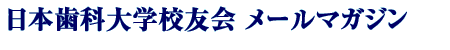 |
第404号 2018年5月1日 |

| 平成30年 | ||
| 5月5日(祝) | ・5・6年全国統一模擬試験 東京校 | |
| 10日(木) | ・3年 特別講義 16時〜 アイヴイホール 新潟校 | |
| 12日(土) | 兵庫県校友会定時総会 17時〜 神戸市 神仙閣 | |
| 17日(木) | ・3年 特別講義 18時〜 九段ホール 東京校 | |
| 19日(土) | 北海道校友会定時総会ならびに会員大会 学術講演会 懇親会 北見市 ホテル黒部 静岡県校友会総会 歯学会学術講演会 17:30〜静岡市 中島屋グランドホテル |
|
| 24日(木) | ・学生健康診断 休講 東京校 | |
| 26日(土) | 校友会本部第131回定時総会 14時〜 富士見ホール ・6年本試験①開始(〜27日) 新潟校 |
|
| 6月1日(金) | ‣創立記念日 ジュビリー5025 | |
| 2日(土) | ‣歯学会総会 13時〜 九段ホール 77回卒後30周年記念事業 18時〜 ホテルグランドパレス |
|
| 9日(土) | ・浜浦祭(〜10日) 新潟校 山梨県校友会総会 14時〜 甲府市 アーバンヴィラ古名屋ホテル 秋田県校友会定時総会 16時〜 秋田市 秋田ビューホテル 大阪府校友会定時総会・懇親会 18時〜 大阪市 大阪マリオット都ホテル 東京都校友会定時総会 18時〜 生命歯学部 |
|
| 11日(月) | ・定期健康診断(〜13日) 新潟校 | |
| 16日(土) | 青森県校友会総会 15時〜 青森市 ホテル青森 長野県校友会通常総会 15時〜 上田市 東急REIホテル 香川県校友会定時総会 15時〜 高松市 JRホテルクレメント高松 愛媛県校友会総会 15時〜 松山市 松山全日空ホテル |
|
| 17日(日) | 愛知県校友会定時総会 12時〜 名古屋市 名古屋栄東急REIホテル | |
| 23日(土) | 福島県校友会総会 14時〜 福島市 福島県歯科医師会会館 | |
| 24日(日) | 千葉県校友会総会 15時〜 千葉市 京成ホテルミラマーレ 栃木県校友会総会学術研修会 13時30分〜 宇都宮市 ホテルニューイタヤ |
|
| 29日(金) | ・6年前期授業終了 東京校 | |
| 30日(土) | 宮城県校友会定時総会 17時〜 気仙沼市 気仙沼プラザホテル 島根県校友会総会 懇親会 17時45分〜 松江市 松江ホテル一畑 |
1.メールマガジン403号を掲載しました。(4/23)
*趣味の世界で異能を発揮している校友の情報をお寄せ下さい 自薦・他薦可
ホームページ「Hobbyな人々」に掲載します

| D Muse 2018 開催される |
4月22日(日)に九段ホールでD Muse 2018が開催され参加者は104名であった。講演は生命歯学部接着歯科学講座 奈良陽一郎教授による「これからのメタルフリー修復を貴方に CAD/CAM修復の勘所」と、ゴディバジャパン(株)ジェローム・シュシャン代表取締役社長による「ターゲット ゴディバはなぜ売上2倍を5年間で達成したのか?」が行われた。
※画像が見られない方はこちら |
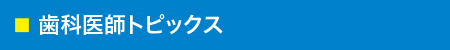
| 1.骨と同成分の材料開発 九大、歯科で製品化「医療新世紀」 4月24日 共同通信社 |
九州大の石川邦夫(いしかわ くにお)教授(歯科・生体材料学)は、骨の主成分である「炭酸アパタイト」を顆粒(かりゅう)状にした新しい人工骨材料を開発し、歯のインプラント手術にも使える製品として実用化したと発表した。 |
| 2.保険料は誰のため?苦境の健保組合、4割は高齢者へ 4月23日 日経新聞 電子版 |
健康保険組合連合会(健保連)は23日、2018年度の予算集計を公表した。健保組合は、多くの会社員が自身の病気やケガへの備えと考えている医療保険制度だが、従業員と企業が負担する8兆円余りの保険料収入のうち、4割強は高齢者の医療費を賄うための「仕送り」に回る。その苦境をみると、誰のために保険料を払っているのか、との疑問も浮かぶ。 |
| 3.「医療ビッグデータ」提供へ始動 カルテなど集めて匿名化、企業・研究機関に 4月22日 朝日新聞 デジタル |
診療録(カルテ)や検査データなど個人の医療情報を集めて企業や研究機関に提供する新制度が5月に始まる。国が認定した民間事業者が病院などから実名で集約した情報を匿名化して「医療ビッグデータ」として提供する。情報の漏洩(ろうえい)や悪用を懸念する声もあるが、副作用の発見や新薬の開発、病気の早期診断に役立つと期待されている。 |
| 4.オンライン服薬指導実現を 規制改革推進会議が意見 4月21日 毎日新聞 |
政府の規制改革推進会議は20日、全ての医療サービスを在宅で受けられるようにするため、オンラインでの服薬指導の実現を求める意見を公表した。5月にも策定する答申に盛り込むことを目指し、関係省庁と協議を進める。 |

| 在学生の校友会メールマガジン配信登録について |
| 平成28年より在学生の校友会メールマガジンの配信登録が開始されました。登録すると年約36回のメールマガジンが月曜日に送信されます。登録は校友会ホームページからお願いします。 |
| 校友会会費納入の確認について |
※新卒者は入会時に4年分の会費を納めていただいております。 4年後(今年は103回卒)からの会費納入をお忘れないようにお願いいたします。 その後2年間未納の方は自然退会となりますのでご注意ください。 最近、送付物等が校友会から届かない会員の方は、事務局までお問い合わせください。 |
| 校友会会員専用ページ |
| 会員のみが閲覧できる専用のページがあります。校友会本部HP上で、「会報バックナンバー」の表示をクリックしたときに「ユーザー名」欄、「パスワード」欄のある画像が出ましたら校友会・歯学会会報のクリップボードに掲載されている記号数字をそれぞれ半角で入力をお願い致します。 このページからコピー&ペーストされても結構です。ユーザー名およびパスワードは大切に保存をお願い致します。 |
| メールアドレス登録・再登録のお願い |
| 校友会本部では、インターネットが会員への情報伝達を効率化、迅速化する上で有力な手段であると考えています。ぜひとも大多数の会員が本会から発せられるインターネットでの情報を受信できるよう、普及にご協力ください。お知り合いの会員で、まだ登録されていない、あるいは登録したけれどもメールマガジンが届かないという方がいらっしゃいましたら、 校友会本部HP(http://www.koyu-ndu.gr.jp/)でのメールマガジン登録あるいは再登録をお勧めください。 |



